注文住宅の家づくりをはじめようとしたとき、何から始めればいいのかよく分からないという方は多いようです。
それは、注文住宅の流れが把握できていなことが大きな理由のひとつだと考えられます。
 管理人
管理人そこでここでは、注文住宅の流れについて分かりやすく解説します。
それではまいりましょう!
この記事では、当サイト監修役のファイナンシャルプランナーである鈴木さんに、注文住宅の契約までの重要ポイントを解説してもらいます。
元ハウスメーカー社員であった経験からも貴重な内容をお伝えいただきます。
家づくりで注文住宅の流れを理解するべき大切な理由とは?



注文住宅で理想の家づくりを成功させるためには、「注文住宅の流れ」を理解して進めることがポイントです!
家づくりで「注文住宅の流れ」をよく理解しないで家づくりを進めた方の中には、それが原因で次のような後悔を感じている人が少なくありません。
注文住宅の流れを理解しないで進めて後悔の例
- 「もっとああしておけばよかった」と失敗に感じることが多く、今さら悔やんでも悔みきれない残念さを感じる。
- 毎月の住宅ローンの返済がキツくてゆとりある生活ができないし将来も不安。
- 家づくりでは、悩みやストレスが多く苦労ばかり感じた割に、満足感が得られていない。
- 念願のマイホームを建てたのに家族が不満を持ち、愚痴を聞くのが辛い。
このように「注文住宅の流れ」を理解してスケジュールに沿ってひとつひとつの工程をクリアしていかなかったばかりに「家づくりに失敗した」と後悔するなんてことは絶対に避けたいですよね。
そこでここでは、家づくりのスケジュールを見ながら、「注文住宅の流れ」について理解を進めましょう。
元ハウスメーカーで働いた経験のあるFP鈴木さんが分かりやすく説明してくれるので、きっと「注文住宅の流れ」の理解が深まり、あなたのスケジュール作成に役立つと思いますよ。
それでは、まいりましょう。
最適な住宅メーカーと契約することが成功のカギ!
自分たちにとって、理想の家づくりを成功させるためには、最適な住宅メーカーと契約することがカギとなります。
最適な住宅メーカーとは、希望や要望、そしてこだわりを実現して叶えてくれる会社です。
それは、大手ハウスメーカーであるかもしれないし、地元密着型の工務店や設計事務所であるかもしれず、人それぞれによって違います。
数ある住宅メーカーから、最適な会社を選び契約することができるかは、注文住宅の流れを理解し、しっかりとしたスケジュールに沿って家づくりを進められるかどうかにかかっていると言えるでしょう。
あなたの夢を叶えてくれる最適な住宅メーカーを見つけて契約するためのスケジュールを考えてみましょう。
家づくりのスケジュール



「家を建てる決心はしたけれど、何からはじめればいいのか分からない。」という方は多いです。
そこで、まずは家づくりのスケジュールを見ていただき、スタートから完成までの流れのイメージを掴んでいただきましょう。
家づくりにかけることができるお金を計算して予算を検討します。
家を建てるにはどんな費用がかかるかを把握して、家づくりの費用を概算で出します。
どんな暮らしがしたいのか、どんな家にしたいのかなど、新しい家に対する希望や要望を出していきます。
こだわりたいこともはっきりとさせておきましょう。
ポイントは、家づくりノートにしっかりと書いておくことです。
本やネットで情報収集をして、家づくりの基礎知識を身に付けましょう。
住宅メーカー各社の資料は、ネットの一括資料請求サイトを活用することで、簡単便利に効率的な資料収集ができます。
実物を実際に見たり体感することで、理想の家づくりのイメージをさらにふくらませることができます。
この段階で大切なことは、あくまで見学をすることが目的で、住宅会社を決めることではないことを強く意識しましょう。
理想の家を予算内で建ててくれる住宅会社を探します。
できるだけ多くの住宅会社を訪問して、気になったことはすべてメモをして比較検討していきましょう。
この段階で、候補の会社を2から3社に絞ります。
土地購入も必要な方は、土地探しも同時に進めます。
土地探しは、住宅会社に相談しながら、不動産会社の情報もチェックします。
ラフプランと概算見積もりを比較検討して、自分たちにとって最適な依頼先を決定します。
理想の家づくりに成功できるかは、依頼先がカギになるので、ここでは慎重に決めます。
敷地にかかる法規制の確認や、敷地境界線の確認を行います。
地盤調査を行い、地盤改良や造成の費用が算出されます。
住宅会社を選択する際に作成されたラフプランをもとに本プラン(本設計)に進みます。これまでにも要望や希望、そしてこだわりなどを伝えてあると思いますが、さらに細部まで確認しながら設計に入ります。
本設計ができあがると、本見積もりが作成されます。
設計契約、工事請負契約を行います。
ここで契約を済ますと「やっぱりもう一度考え直したい」というような後戻りはできないことになるので、契約前には念入りな確認を行いましょう。
本工事の第一歩となる基礎工事が始まります。
家の土台となる大切な工事ですが、家が建ってからはなかなか見ることができない部分ですから、工事中もしっかりとチェックしましょう。
本工事の第一歩となる基礎工事が始まります。
家の土台となる大切な工事ですが、家が建ってからはなかなか見ることができない部分ですから、工事中もしっかりとチェックしましょう。
上棟とは、一般的に家の最上部に棟木(むなぎ)が出来上がった状態のことを言いますが、家の建築工法や建築構造などによってタイミングに違いがあります。
造作工事、内装・設備工事が進められていきます。
工事は着々と進められていくので、依頼内容通りになっているかをチェックしていくことも大切です。
竣工とは、建築工事がすべて終了した状態です。
完成検査は、建築基準法で定められた必ず行う必要のある検査です。
建築会社がハウスメーカーや工務店の場合は、依頼会社にまかせておけば大丈夫です。
施主検査は、施主と住宅会社がいっしょに完成した建物全体をチェックすることです。
図面を見ながら、じっくりと時間をかけてチェックしましょう。
完成検査、最終チェックで見つかった直しが完了した後に引き渡しが行われます。
保証内容の確認や、新居の鍵の引き渡しなどが行われ、引き渡し関連の書面に署名と捺印をします。
引き渡しが無事に済めば、引っ越しが行われて新居での新生活がスタートです。
家づくりのスケジュール解説



家づくりのの各スケジュールの項目について、解説していきます。
Step1 予算検討
注文住宅の家づくりでは、さまざまな費用がかかります。
大きく分けると、建物本体にかかる本体工事費をはじめ、本体以外の工事にかかる付帯工事費や、各種手数料や保険料や税金などにかかる諸費用などです。
それぞれの中に、細分化された費用があり、そのひとつひとつの費用を予算化するのは、とうてい無理です。
予算を検討する方法としては、上記の3つの費用(本体工事費、付帯工事費、諸費用)にどれくらいのお金がかかるかを想定して予算金額を設定します。
それぞれの費用は、総費用に対して次の表の割合が目安になります。
| 本体工事費 | 70~75% |
|---|---|
| 付帯工事費 | 15~20% |
| 諸費用 | 5~10% |



注文住宅ではすべてを把握することは難しいほどの様々な費用が発生します。とはいえ、曖昧な予算で家づくりをスタートするのは失敗のもとになり危険です。
3つの費用にかかるお金をしっかりと算出して予算化に取り組みましょう。



予算オーバーを防ぐ予算の建て方を記事にまとめましたので、参考にしてみてください。


Step2 新しい暮らしのイメージ作り
注文住宅の魅力って何かを考えたとき、「自分たちの希望や要望、こだわりを形にできて暮らすことができる。」ということが最大の魅力であることは間違いありません。
つまりそれは、注文住宅だからこその魅力を最大限に活かすことができれば、満足できる理想の家づくりになることを意味します。



そこで、注文住宅の流れの第一歩として、新しい家でどんな暮らしがしたいのかを頭をフル回転させてイメージしてみましょう。
それはあなただけではなく、家族全員の要望や希望を出せるだけ出して、ノートに記録していきます。
もちろん、注文住宅だからといってすべての要望や希望が叶うとは限りませんし、設計プランの段階で諦めなくてはならないこともでてくるでしょう。
検討に検討を重ねて諦めなくてはならなくなったことについては、残念であっても納得した気持ちになれるでしょう。
でも、家が建った後に「ああしておけばよかった」とか「要望してみるだけ要望してみればよかったかも」と思うことは後悔につながります。



「こんなことを要望しても無理かな?」とか「笑われて恥をかくかも」と自分で判断してしまわず、住宅会社に伝えてみると、そのままとはいかないまでも、別案で近いものを実現してくれる場合も多々あります。



私の家づくりでも、無理かもと考えていたことが実現できたりしました。
例えば、お気に入りの書斎や妻の家事コーナーなどがそうですね。
設計士さんがいろいろとアイデアを提案してくれてよかったです。
実現できるかできないかは、これから先に何度も考える機会はあるので、今はとにかく、思いつくだけの要望や希望、こだわりを出して記録していきましょう。
ここで大切なのは、家族誰もの意見をお互いに絶対に否定しないことです。
家族であってもお互いに尊重し合う気持ちでひとつひとつの意見を聞き、「それは無理」とか「それは嫌、こっちの方がいい」というのはこの段階では絶対に言わないようにすることが大切です。
無理かどうかは住宅会社のプロの判断も参考にして、どれがいいのかはモデルハウスやショールームで実物を見たり触れたりして体験してみて決めていくといいでしょう。
もちろん、概算見積もりを見て予算との検討も判断材料になっていきます。
注文住宅では、これから先、取捨選択の判断をする機会は多々あるので、最初から取捨選択をする必要はないと言えますね。
注文住宅だからこそ実現できる「新しい家でどんな暮らしがしたいのか」をイメージして、じっくりと考えてみましょう。
Step3 基礎知識のための情報収集



注文住宅で理想の家づくりを成功させたいとお考えならば、家づくりの勉強は避けて通れないと言っていいでしょう。
家の構造のことや建築工法のこと、住宅の最新技術のこと、暮らしやすい間取りや導入する設備のこと、資金計画に関わる費用や住宅ローン、税金のこと、はたまた住宅建築に関わる法律のことまで、様々なことを勉強する必要があります。
家づくりの勉強と一言でいっても、「これ一冊ですべてOK!」というような教科書的なマニュアルがあるわけではありません。
例えば、間取りのことだけで何冊もの本がありますし、住宅ローンの本であっても同様です。
しかし、家づくりの専門家になるわけではないので、やみくもに何冊もの本を買って読む必要はありません。
大切なことは、住宅会社の営業マンや担当者と話をするときに、お互いの意思疎通がスムーズにできる程度の知識を身に付けておくことです。
家づくりで失敗したと後悔している方の理由のひとつに、「勉強不足で依頼した会社に任せてしまったため、自分が暮らしたい家にならなかった」というものがあります。
これは、営業担当者が悪いとばかりは言えず、知識不足のまま家づくりを進めたことが原因と言えるでしょう。
では、どのようにして家づくりの勉強をすればいいのでしょうか?



ネットの【無料】一括資料請求が効率的でおすすめです。
住宅メーカーのカタログは、家づくりに関する最新情報の宝庫です。
メーカーが販売している家の紹介だけではなく、家づくりの知識吸収に役立つ最新情報をたっぷりと見ることができます。
多くのメーカーでは、商品のカタログだけでなく、家づくりに関するパンフレットや小冊子などを無料配布しています。
それらの中には、一般書籍に勝るとも劣らない役立つ優れものもあるので、手に入れておいて損はありません。
カタログを手に入れる方法というと、住宅展示場のモデルハウスに行ってもらってくることを想像する方が多いのですが、今の段階ではネットの一括資料請求を利用するのがおすすめです。
まずはネットでたくさんのカタログや住宅関連資料を手に入れて、知識を得てから住宅展示場に行くのが効率もよく理想的です。
住宅メーカーのカタログを見てからその会社に行くのと、見ないで行くのとでは、カタログを見てからの方が訪問する価値がグンと高まりますし、気持ちに余裕を持って行けます。


Step4 建物見学(モデルハウスや見学会)
ある住宅・不動産情報サイトの調査によると、家を建てると決めた人の約9割が最初にすることが、住宅展示場に行くことだったそうです。



「家を建てると決めたけれども何からはじめていいのか分からないから、とりあえずハウスメーカーの家が建ち並ぶ住宅展示場に行ってみよう。」という人がいかに多いかが分かりますね。
住宅展示場の出展には多額の維持費がかかると言われていますが、それだけのお客さんが集まるということは、費用対効果が見込めるので、ハウスメーカーは全国に出展しているのです。



住宅展示場の存在は知っていても、家を建てると決めるまで一度も行ったことがないという方が多いと思います。住宅展示場は気軽に行ける場ではありますが、家づくりの知識を持ってから行くと訪問価値はグンと高まります。
この上でもお伝えしましたが、家づくりの知識もほとんどなく、カタログにも目を通していない状態で建物見学をしても、「ああやっぱり、新築っていいいよなあ。こんな家に早く住みたいなあ。」というような憧れの気持ちで胸がいっぱいになるだけの見学になってしまうかもですよ。
でも、ここまでお読みになられたあなたなら、住宅展示場に行く前の準備はしっかりとできているはずですから安心です。
堂々と自信を持って建物見学に行きましょう!
ただし、ここで大切なことは、あくまで見学が目的であって、住宅メーカーを選ぶことが目的ではないことを明確にしておくことです。
住宅展示場のモデルハウスに行けば、必ず営業マンのセールス活動を受けることになります。
相手はそれが仕事ですから仕方がありませんし、プロの営業ですからその気にさせられような営業トークも聞かされることになります。
しかし、今は住宅メーカーの比較検討をするための見学であることをしっかりと伝えて、誘惑的な言葉もグッとこらえるようにしましょう。
とはいっても、もしかしたら将来的にパートナーとなる会社になるかもしれないので、営業活動を毛嫌いするような態度をとらないことも大切です。
お互いの立場を理解し合って接しあえるといいですね。



さて、建物見学は住宅展示場にあるモデルハウスの見学以外にもいくつかありますので、ここで主な建物見学についてまとめてみます。
建物見学の種類
- 複数のハウスメーカーが一箇所に出展している住宅展示場の「モデルハウス見学」
- 住宅展示場に出展していない住宅メーカーが独自に展示している「展示住宅見学」
- 完成したばかりの新築の家を見学できる「完成現場見学会」
- 建築途中の工事現場の様子や家の構造を見ることができる「構造見学会」
- 実際に入居されている家に入って見学したり住人に直接話を聞ける「入居者宅見学会」
上記の中の見学は、予約や連絡なしで行くことができますが、見学会はあらかじめ予約もしくは連絡を入れておく必要がある場合が多いです。
この他にも、大手ハウスメーカーなどでは、自社工場の見学するバスツアーなどを企画する企業もあります。
建物見学は、実物を見たり触れて体感できたり、カタログでは分からなかったことや疑問を解決できたりできるので、積極的参加するといいと思います。
参加する際には、ノートと筆記具、メジャーなどを持参して、しっかりとチェックして記録しておきましょう。
Step5 住宅会社探しと土地探し
土地探しは、不動産会社を訪ねることがポピュラーな方法です。
不動産を扱う会社にも種類があり、ネットワークも情報も豊富な大手不動産会社や、地元に密着して営業をしている地域密着型の不動産会社、銀行系の不動産会社(相続に絡み売り出された不動産情報が多い)などの他、住宅メーカーが独自で不動産を扱っている場合もあります。
どの不動産会社なら、自分がほしいと希望する土地を購入できるかは、まったく分かりません。
ネットワークが強みの大手不動産会社だからといって、必ずしも希望の場所に希望の広さの土地を所有しているというわけではありません。
小さな地元密着型の不動産会社が、地元に密着しているがうえに、顔見知りの地主から条件の良い土地を購入している場合も少なくありません。
銀行系は、相続に絡んだ土地を売りに出していることから、掘り出し物ともいえるような良い土地を探し出せるという話も聞きます。



建てる家の住宅メーカーが決まっているならば、住宅メーカーに土地を相談することをおすすめします。
住宅メーカーならば、自社の家を建てるのに条件が適した土地を紹介してくれますし、住宅メーカー所有の土地であれば、仲介手数料が必要ないのもメリットです。




住宅会社探し
家づくりの基礎知識を身に付け、資金計画も済ませた段階ですから、どんな家を建てたいのかのイメージはつかめていると思います。



この段階で、希望や要望の優先順位をきめて、住宅会社にしっかりと伝えられる準備をします。
こだわりたいことも、明確に伝えられるようにしましょう。
プラニングには、ライフルホームズで一括資料請求するともらえる「はじめての家づくりノート」が役立ちます。
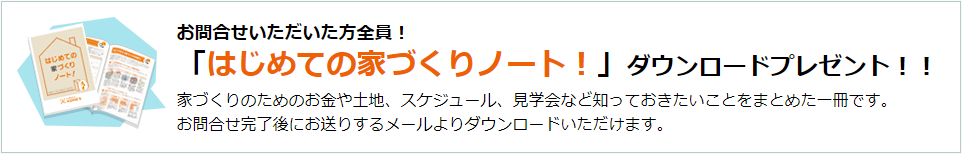
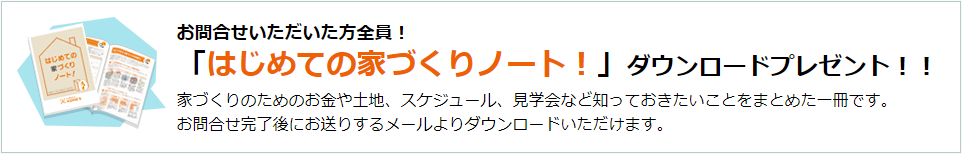


このノートには「理想の住まいをプラニングしてみよう」というプラニングのためのページが6ページあります。
画像は、その最初のページですが、プラニングのポイントになる項目を記入していくようになっていて、自然にプラニングを完成できます。



プラニングをまとめられたら、いよいよ本格的に住宅会社選びの行動に入ります。
資料収集の段階で、「タウンライフ家づくり」や「ライフルホームズ」を利用された方は、それぞれの住宅会社の営業担当者が分かっているはずです。
また建物見学に行った際にも、営業担当者の名刺を受け取っているはずです。
営業担当者が分かっている住宅会社を訪問する場合には、あらかじめアポイントの電話をしてから訪問することをおすすめします。
もちろん営業担当者は喜んで対応をしてくれますし、話をスムーズに進めることができます。
このとき忘れないように持っていきたいのは、「はじめての家づくりノート」です。
話をしている中で、このノートをパラパラめくったり、しっかりと記入していくと、営業担当者は心の中で「このお客さんは家づくりのことをしっかりと研究しているな」と思うはずです。
そして営業担当者は、あなたのことをしっかりと対応しないといけないなという気持ちが強くなるはずです。
Step6 依頼先を決定!
注文住宅会社が提案するプランと概算見積もりが揃ってきたら、じっくりと検討します。
「家づくりノート」や、これまでに集めてきたカタログや資料などをなんども見直しながら、依頼先の候補を絞っていきます。



気になることや、分からないことがあったら、遠慮なくどんどん質問することをおすすめします。
高い買い物をするのですから、遠慮する必要はまったくなく、些細なことでも聞くといいですね。
そのときの、営業担当者の態度や質問に対する回答の質なども住宅会社選びのポイントしてチェックしておきましょう。
例えば、売り込みばかりして、質問に対する答えが曖昧なような営業担当者の場合は、会社の姿勢もうかがい知ることができると判断してもいいかもですよ。
依頼先候補の住宅会社が2社から3社程度に絞ることができたら、その会社とはしっかりと打ち合わせを行います。
そうしていくうちに、「ここなら自分たちの理想の家を建ててくれる」と思える1社が見えてくると思います。
候補にあがった他の会社には断り辛い気持ちになるものですが、「家族でしっかりと何度も検討した結果、○○さんにお願いすることにしました。本当にいろいろとありがとうございました。」というように、お礼の言葉を添えて断りましょう。



「そんなことを言わずに何とかうちで」と言ってくる営業担当者もいるかもしれませんが、私の経験では、案外あっさりと身を引く感じの印象でした。
おそらく、営業担当者もプロですから、もう気持ちを固めたお客さんの心を動かすのは難しいことは承知しているでしょうし、サクッと諦めて他のお客さんに力を注いだ方がいいと考えるのだと思います。
Step7 敷地・地盤調査
敷地調査
家はどんな土地にも、どんな大きさの家を建てるというわけにはいかず、法規制に関わる調査を行います。
敷地の測量を行い、登記簿との照合によって相違がないかを調査したり、水道・下水道・ガス・電気等の配管整備状況などを調査します。
また、敷地には、建築基準法や都市計画法などの法律による規制があるため、その土地にどのような家を建てることができるかは法律の範囲内となります。



建築基準法や都市計画法などの土地に関わる法的規制は、土地のある場所によって内容に違いがあるので、しっかりと確認しましょう。
敷地調査を行わないと本プランの図面設計に入れないため、必ず行う必要がありますが、費用については依頼先の住宅メーカーもちの場合が多いので確認しましょう。
地盤調査
家を建てる土地の地盤調査は必ず行います。
それは、その土地に家が建っていたとしても同様です。
新築住宅の大きさや建築工法などによっても、地盤に必要な硬さが変わってきます。
例えば、鉄骨構造プレハブ住宅などは、木造住宅に比べて家自体が重いので、強固な地盤にしなければなりません。
どれほどの大きさの地震が、いつどこでおきるかわからない国ですから、地盤調査に従った地盤改良を行いましょう。


Step8 本プラン設計・本見積もり作成
これまでの打ち合わせをもとに本プラン(設計図面)と本見積もりの作成となります。
プロが作成する設計図面は、ふだん目にすることが少ないため、簡単に理解できないかもしれませんが、しっかりとイメージしてチェックしましょう。
また、3Dイメージや住宅モデルを作成してくれる住宅メーカーも多いので、それらでもチェックしましょう。
少しでも分からないと感じたことや、確認したいことがあれば、営業担当者や設計士に相談することが大切です。
コンセントの数や位置に問題はないか、ドアどうしが干渉してしまわないか、窓の位置は隣の家の窓と重なったりしないか、デッドスペースはないか、配管は外配管になっていないかなど、家が建ってからではなんともならない部分はしっかりとイメージして確認しましょう。
本見積もりは、予算オーバーしていないかを確認します。
ここで注意しなければならないことは、カーテンや照明器具などは、本契約後(工事着工後)に決めていく住宅メーカーが多いということです。
「えっ!そうなの?」と思われた方も多いと思いますが、そうなんです。
後になって慌てないためにも、本見積もりには何が含まれていて、何が含まれていないかをしっかりと確認しておくことがポイントになります。
Step9 本契約
工事請負契約書に署名と捺印をして正式契約を結びます。
ここで大切なことは、工事請負契約書だけでなく、同時に提出される工事請負契約約款、設計図書、工事仕様書、見積書に書いてあることをしっかりと確認することです。
とくに工事請負契約書と工事請負契約約款の内容は熟読して、間違いや漏れなどがないかチェックすることが大切です。
契約書というと、細かい字でギッシリと書いてあるもと思われるでしょうが、それは間違いありません。
「めんどうだし、相手を信じているから適当に読めばいいや」と考える人もおられると思いますが、何十年と長く暮らす家ですから、めんどうと考えずしっかりと読みましょう。
もちろん、気になることや分からないことは、営業担当者に確認することが大切です。
おすすめの方法としては、契約を交わす予定日の数日前に契約書類のコピーをもらい、自宅でじっくりとチェックすることです。
Step10 着工(地鎮祭)
住宅会社が工事のスケジュールを組み工事が始まりますが、工事の前には地鎮祭を行うのが通例です。
地鎮祭は、地を鎮めると書いてある通り、土地の神様を鎮めるお祭りです。
「どうぞ神様、この地に家を建て暮らすことをお許しください。安全に事故がなく無事に家が建ち、幸せに暮らせますようお願いします。」と、お許しとお願いを伝える大切な行事です。
地鎮祭を行わないという施主は少ないのですが、「行わない」という施主もおられるようです。
個人の自由といえばそれまでなのですが、これから家づくりを進めていただく工事関係者の方達にも気持ちよく作業をしていただくためにも、地鎮祭は行っておくべきかと思います。
Step11 基礎工事
基礎工事に入る前に行われるのが「地縄張り」です。「縄張り(なわばり」とも言います。
地縄張りとは、敷地内の建物が建つ位置を明確にするために縄を張ることです。
縄といっても、最近では縄ではなくロープやビニル紐が使われることが多いです。
地縄張りは、業者が図面通りに行いますが、施主としても建物の配置図をもとにしっかりと確認しましょう。
地縄張りが完了すると、いよいよ本格的に基礎工事が始まります。
ご存知の通り、基礎は家の土台となるとても重要な部分です。
実際に建物が建ってしまうと、基礎の内部はなかなか見ることができないので、基礎工事が行われている様子はときどきチェックしましょう。
Step12 上棟、屋根工事
建物本体の工事が始まります。
建築工程は、建築工法などによって違いがあります。
木造住宅の例では、基礎に土台敷きが行われ、柱、梁、母屋などの構造材を組み立てます。棟木を上げて上棟式となります。
最近では、上棟式を行わない施主も少なくないようですが、これから先の工事の無事を願う行事ですし、注文住宅の家づくりをする人だけが体験できる式ですから、行っておくといいのではないでしょうか。
棟上げの段階では、おおまかな骨組みが出来ている状態なので、次に躯体工事と屋根工事に進みます。
Step13 外壁工事、内部造作工事、内装・設備工事など
柱や梁、屋根などの建物の主要構造部が出来上がってくると、それ以外の工事が着々と進められます。
それらの工事のほとんどは、それ専門の業者が工事を担います。
日毎に変化する家の内外装をよくチェックすることも大切です。
ただし、様々な工具が置かれていたり、設置途中の部材などもあるので、それらには触れないように細心の注意をはらいましょう。
Step14 竣工
竣工(しゅんこう)とは、建築工事が完了したことを意味します。
一般的に竣工という言葉には馴染みがない方も多いと思いますが、工事の終わりという意味で竣工といいます。
マイホームが完成したと同じと考えて間違いではありません。
ただし、竣工したからと言ってすぐに暮らし始めることができるわけではなく、次の「完成検査」が行われます。
Step15 完成検査
完成検査とは、施主が家のチェックを行う検査ではなく、建築基準法に基づいて行われる新築住宅の検査で、「完了検査」ともいわれます。
完成検査は、出来上がった建物が建築確認申請で許可を受けた図面通りに作られているかのチェックがされます。
出来上がった建物が、建築確認申請の図面と違っていては申請が嘘となってしまいますからね。
完成検査後に「完了検査申請書」を各自治体の担当先などに提出を行いますが、これらはすべて住宅会社が行うので心配はいりません。
完成検査とは別に、施主と住宅会社とで、施主検査を行います。
工事に誤りや不備はないか、設備機器はちゃんと動作するか、キズや汚れはないか、歩いてみてキシむ音がするようなところはないか、ドアや戸・窓の開閉はスムーズか、などなど時間をかけてチェックしましょう。
修理するべきところが見つかった場合には、修理工事が行われます。
Step16 引き渡し
ついに待ちに待った新居の引き渡しです。
でもまだ気を緩めないでくださいね。
保証内容の確認をしっかりと行い、引き渡し関連の書類に目を通して、署名と捺印をします。
同時に設備関係の使用説明書や保証書などといった書類も受け取ります。
どの書類も重要なものばかりですから、大切に保管しましょう。
私の場合は、工事関係者が使用した鍵の破棄を確認し、我が家の鍵を受け取ったら引き渡し完了でした!
これまでの苦労がすべてふっとぶ瞬間でもあり、これからの生活にワクワクが爆発しそうな気持ちになりました。
Step17 新生活スタート
引っ越しを終えると、いよいよ新居での新生活がスタートします。
すべてが新しいとはいえ、実際に暮らしてみると「ここちょっと変じゃない?」というような不具合を見つけることもあります。
そのときは、遠慮することなく住宅会社に連絡しましょう。







